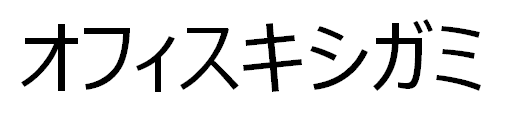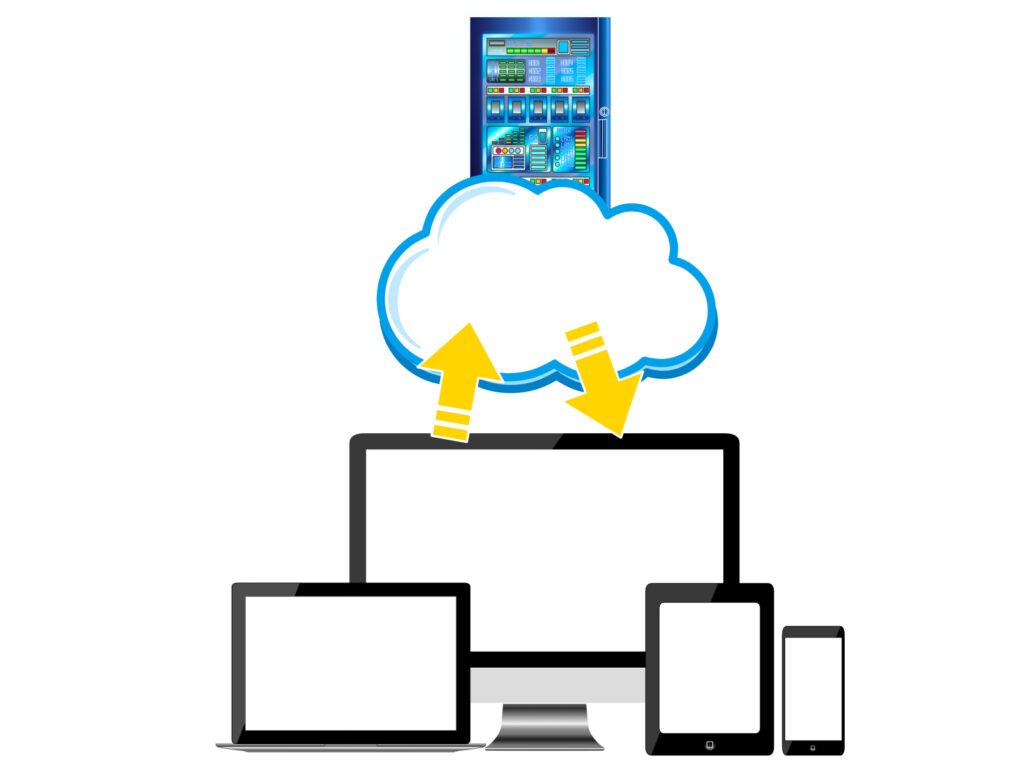中小企業こそオンラインストレージを利用しよう~データ保存の負担軽減~
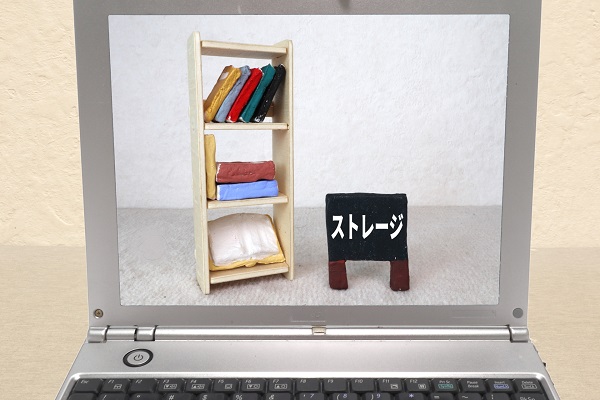
中小企業こそオンラインストレージを利用しよう~データ保存の負担軽減~
オンラインストレージは、日々の管理がほとんど不要であり、ハードディスクの故障によるデータ消失の可能性も無いため、専任のIT担当をおけない中小企業にとって、とても有効なツールです。
本コラムでは、私が感じているオンラインストレージの良さや使い方をまとめています。
目次
中小企業のデータ保存事情
中小企業においては、資料をデータ化していても個々のパソコン内で保存しているケースが多々あります。また、NAS(Network-Attached Storage)を自ら設置してそこに保存しているケースも良く見られます。
パソコンやNAS保存場所であるハードディスクは、耐用期間は短く3~5年でしかありません。そのため、定期的にハードディスクを交換しデータを移し替える等の適切なメンテナンスをしないとデータ消失の可能性が高くなります。
要注意:
多くの電化製品のように故障したら交換すれば良いとの考えを持たれている経営者が多くいると感じています。ハードディスクは故障してしまうとほとんどの場合、保存しているデータを取り出すことが不可能になります。故障する前に対策を取らなければなりません。
しかしながら、中小企業においては管理する人材が不在であることが多く、メンテナンスせずに放置されており、危険な状態にさらされてしまいます。
データ増加に伴う課題
中小企業においてもシステム化やペーパーレス化を進めており、会社のあらゆる情報をデータ化し保存するデータ量が増加していると思います。そうなるとデータ量が増えるにつれてどこに格納するかが課題になります。
主な対策としては次の2点があると思います。
- 古いデータや使われないデータを削除して、空き容量を増やす
- 外付けハードディスクやNAS等の外部記憶装置、オンラインストレージの利用し保存できる容量を追加する
お勧めは2の保存容量を追加することです。1の古いデータや使われないデータの削除は意外とできないものです。データの取捨選択の判断がとても難しいです。
保存できる容量を追加する際に、中小企業の多くは、掛かる費用を考慮して、外付けハードディスクやNAS等の外部記憶装置を選ぶのではないでしょうか。
しかしながら、10年20年使用できるような感覚で外付けハードディスクやNAS等の外部記憶装置を選ぶと痛い目を合うかも知れません。前章でも述べたとおりハードディスクは、耐用期間は3~5年程度しか無いからです。
オンラインストレージは一般的に月額で使用料を払うため長く使うと費用が大きくなると考えがちです。しかしながら、その費用に見合ったサービスを受けることができます。
オンラインストレージのメリットを考えれば、中小企業こそ導入すべきだと考えています。
オンラインストレージとは
オンラインストレージの特徴やメリット
- インターネットがつながる場所であればどこでも接続が可能であり、パソコンだけでなくスマホやタブレットからでも利用できます。基本的に専用アプリをインストールして使いますが、WEBブラウザでも使用でき、必ずしもアプリをインストールする必要はありません。
- 新たに機器を購入する必要がなく、機器の管理や運用も不要であり、導入コストと運用コストを抑えることができます。
- 機器の故障によるデータ消失のリスクはありません。
- 記録容量の拡張を簡単にできます。(費用は追加で掛ります)
- 自動でアプリのバージョンアップ、自動でデータのバックアップが行われるので管理の手間が少なくなります。
企業でのオンラインストレージの利用動向
総務省「令和3年版情報通信白書」によると、2020年においてクラウドサービスを利用している企業の割合が約7割であり、その利用しているサービスの中では「ファイル保管・データ共有」(いわゆるオンラインストレージの利用)が約6割となっています。現在はもっと多くの企業が取り入れていると考えられます。
今やオンラインストレージはもっとも一般的に使用されているクラウドサービスと言えます。
参考:総務省|令和3年版 情報通信白書|企業におけるクラウドサービスの利用動向
その他のデータ保存方法
【外付けハードディスク】
パソコンに内蔵しているハードディスクではなく、パソコンの外部に存在しUSBケーブル等で繋ぐことで使用するハードディスクです。比較的安価です。
【外付けSSD】
SSDは半導体メモリを使った記憶装置のことです。ハードディスクとく比べてSSDは小型で衝撃に強く、読み書きが高速であるという特徴があります。しかしながら、ハードディスクより割高です。
【NAS (Network-Attached Storage)】
外付けハードディスクの一種ではありますが、ネットワーク(LAN等)に接続して使用します。パソコンやタブレット等と1対多での接続が可能となり、複数のパソコン等から同時に接続することができます。
また、RAID機能を使えるものもあり、ハードディスクに障害が生じたときでもデータを再生することができます。比較的高価であり、導入や管理にある程度のIT知識が必要です。
【DVDやBD(ブルーレイディスク)】
知らない方はいないぐらい一般的なデータを記録できる媒体です。データを記録したり読み込むには機器が必要ですが、現在のほとんどのパソコンには標準で備わっています。安価ではありますが、物理的に壊れやすくデータを長期保存するには不向きです。
オンラインストレージを中小企業に勧める理由
IT担当の作業負担が軽減するから
中小企業では、専任のIT担当者を置いていないケースが多いと思います。データ保存に関する作業をできるだけ減らしたいものです。
オンラインストレージであれば、
- 電子機器が必要無いため、機器のメンテナンス作業を削減できます
- IT担当者の運用に関する作業を軽減できます
メンテナンス作業を削減
電子機器は熱やほこりにとても弱いため、機器を導入すると温度管理や定期的な清掃が必要です。また、盗難予防もしっかり行う必要があります。行っていない企業もあるかもしれませんが、その場合はとても危険な状態になっていると思います。
オンラインストレージであればそもそも管理する機器が無いので何もしなくても危険はありません。
運用作業を軽減
IT担当者の負担になる作業として、定期的な最新バージョンへのアップデート、データの残容量の確認、バックアップの運用等が挙げられると思います。例えば、バージョンのアップデートを自ら行うには実施日程決めたり、社員に通知したり、アップデートしても問題ないか事前にテストしたりとかなりの作業量になるはずです。
このような運用作業の大部分をサービス提供側で行ってくれます。また、データの残容量を確認するための使いやすい管理画面が用意されていたり、バックアップやバックアップデータの戻しを簡単にできるようになっていたりします。
これらのことでIT担当者の運用に関する作業が軽減されると思います。
機器の故障によるデータ消失の危険が無いから
電子機器は熱、ほこり、湿気、衝撃等の弱点が多くごく当たり前に故障します。そして機器が故障すると中にあるデータも消失してしまいます。
オンラインストレージであれば、
- ネットワーク上の一部の機器(例えばハードディスクの1つ)が壊れてもデータは消失しない仕組みで保存されています
- 複数のデータセンターにてデータが保存されており、仮に震災等で1つの拠点が停止しても、継続して運用できる仕組みになっています
機器が破損してもデータが損失することはまずありえず、データ消失への不安を解消できるのは大きなメリットになります。
IT化が進んだ企業にとってデータの価値はとても高まりますので、データの安全性確保がとても重要となります。個人的にはデータの安全性を確保できることがオンラインストレージの一番のメリットと考えています。
コストが抑えられるから
オンラインストレージは利用料を支払い続けることになりますので、データを保存する機器を購入したほうが安くなると考えるかもしれません。
しかしながら、機器の場合は、次のコストが必要になります。
- 導入するコスト
運送費、設置費、ソフトウェアのインストール作業費、初期のパラメータ設定の作業費等 - 運用に関するコスト
電気代、設置場所代、IT担当の運用に関する人件費、ハードディスクの交換やデータ移し替え等のメンテナンス費等
単純に機器だけの価格で判断するのは間違いの元になります。また、データが消失した際の被害額は計り知れないかもしれません。
このことから、オンラインストレージを利用する方がコストを抑えられると思います。
オンラインストレージの使い方
操作方法はツールにより異なりますので、各販売会社にお確かめください。
オンラインストレージは、主に次のように使用することができます。
1. 複数の端末からのアクセス
インターネットを経由していつでもどこでも、どの端末からでもアクセス可能です。テレワークで自宅からアクセスや移動時間にスマホやタブレットからアクセスすることができます。
2.大量データの保存
データ容量は無制限に増やすことができるので、大量のデータを保存することができます。機器の耐用年数を気にすること無く、機器の障害によるデータが損失することがないので、長期間データを保存することができます。
3.データのバックアップ
パソコン内のデータのバックアップ先に向いています。パソコンからオンラインストレージへのデータの移動は簡単操作でできます。(ほとんどオンラインストレージアプリでは、ドラッグ&ドロップで移動可能) 機器の障害によるデータが消失することもなくバックアップ先として最適です。
4.ファイル転送
オンラインストレージを介して、社員間でファイルの転送ができます。メールにファイルを添付して送信するのが主流でしたが、オンラインストレージを使えば、ファイルの保存先を相手に伝えるだけで共有することができます。
5.複数人でファイル同時編集
同じファイルを数人での編集することができます。複数人で使う資料、例えば、プロジェクトの管理資料(スケジュール表とかアクションリストとか)を、同時に編集することで作業効率を上げることができます。
オンラインストレージの不便な点
オンラインストレージにはメリットが多いのですが、1点不便な点があります。
それは、通信に時間が掛かることです。
インターネットを介してストレージに接続するため、ファイルのアップロードやダウンロードに時間が掛かります。そのため、自社でNAS等のストレージを使っていた場合、オンラインストレージに移行すると、速度の違いが明らかなのでストレスを感じる可能性があります。
オンラインストレージに移行するかどうかは、業務に適する通信速度を確保できるかどうかをまず検討する必要があると思います。
気を付けること
社内でのデータ共有をメインで行いたい場合は、オンラインストレージ以外にも最適なアプリがあるので気を付けてください。例えば、グループウェアはオンラインストレージの機能だけで無く、カレンダー(スケジュール)の共有やチャット機能等、社員間の情報を共有するのに便利な機能も持ち合わせています。ノウハウや知識を共有するのであれば、ナレッジ管理システムの方が向いている場合もあります。
使う目的をしっかりと考えて、それに合わせたアプリやソフトウェアを選ぶことが重要になります。
弊社は、アプリ・ソフトウェアの導入自体の支援だけで無く、デジタル化で経営課題をどのように解決していくかの計画立案や運用改善の支援も行っています。企業のデジタル化に課題があり解決させたい場合には、弊社が支援致します。お気軽にお問い合わせください。
弊社は、オンラインストレージの販売会社と関係があるわけでは無いので、公平な観点でオンラインストレージの導入効果を評価することができます。
投稿者プロフィール